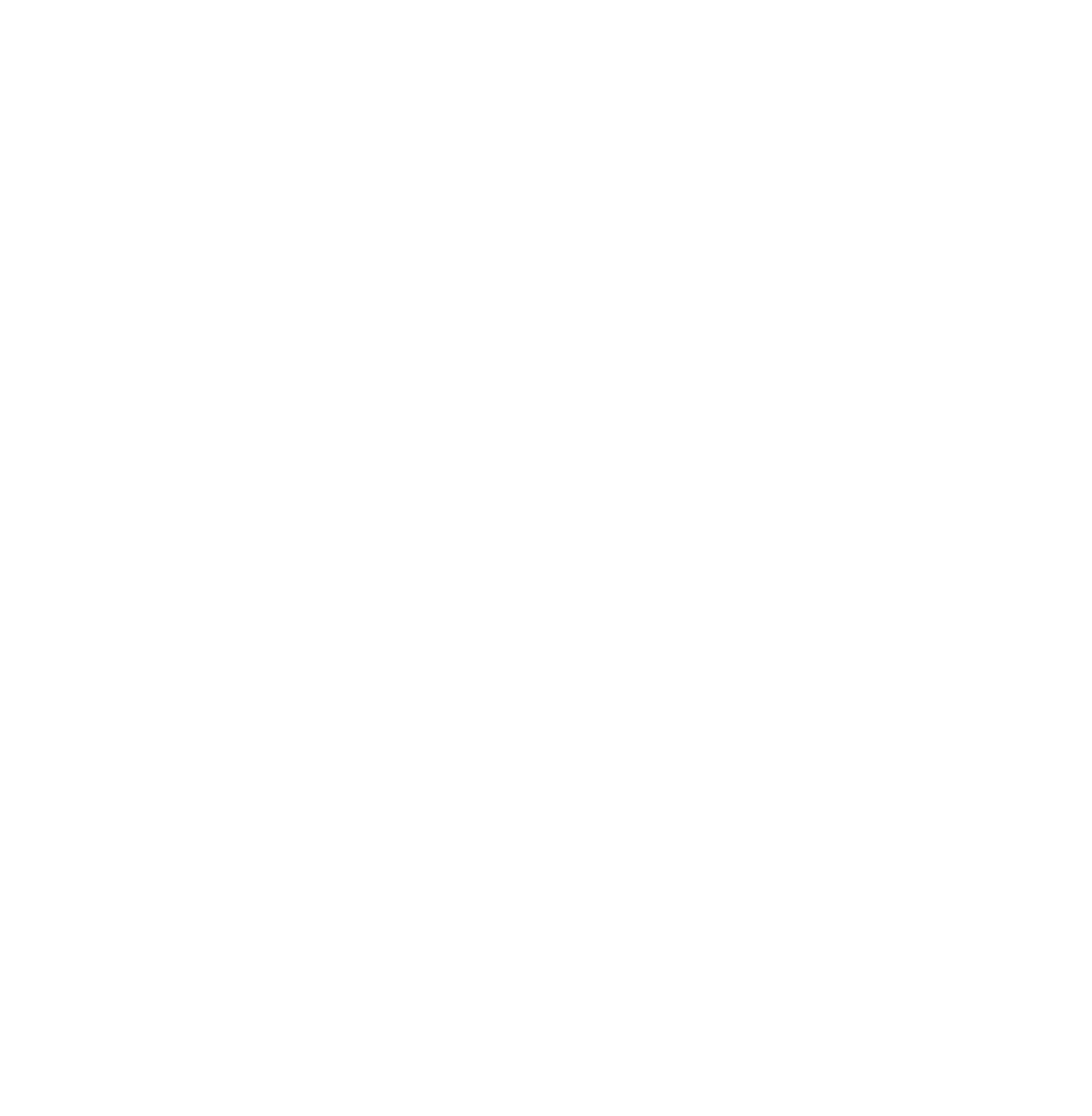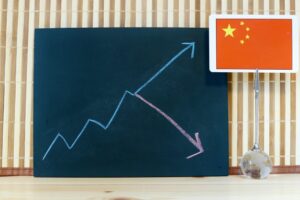2015年の中国化粧品小売売上総額は4844億元(およそ7.9兆円)にのぼり、2018年までにこの規模は8千億元(13.6兆円)を超えようかと言われています。その成長率は、相対的に鈍化しているとはいえ年間20%以上と予測されており、注目すべき市場であることは間違いありません。(参考:中商産業研究院)
訪日中国人に大人気の日本の化粧品、「中国における化粧品輸入国ランキング(2015年)」では日本は2位につけていますが、近いうちに転落すると見られています。その理由はずばり「中国国内における広告費用への投資額」の小ささです。
では実際、他国のブランドは中国でどの程度投資をしているのでしょうか? 今回は各国の代表的なブランドについて、中国における年間のキャンペーン回数とSNS露出件数を収集・分析し、今後取るべき対策について探っていきたいと思います。
調査対象ブランド(製品名含む)
| 資生堂 |
| コーセー |
| カネボウ |
| ロレアル(メイベリン) |
| ディオール |
| ランコム |
| Lanegine |
| イニスフリー |
▼中国の美容市場の概観から攻略までは、セミナーレポートシリーズがガイドします。
【セミナーレポート】China Beauty(1)~中国美容市場、計り知れぬ成長の余白~
目次
キャンペーンが成功していると思われるブランドは?
まずはブランドごと(製品名含む)の中国における年間のキャンペーン数とSNS露出数を比較して見ましょう。
【調査概要】
調査期間:2016年9月~2017年8月
対象SNS:新浪微博上で、各ブランド名(製品名がわかるものも含む)の書き込みを収集
キャンペーン回数についてはWEBサイトを独自調査
SNS露出件数別ランキング
| キャンペーン回数 | SNS露出件数 | |
|---|---|---|
| ディオール | 31 | 592,080 |
| ロレアル(メイベリン) | 44 | 551,056 |
| 資生堂 | 14 | 386,848 |
| ランコム | 29 | 378,564 |
| コーセー | 10 | 192,352 |
| イニスフリー | 24 | 171,716 |
| Lanegine | 39 | 164,384 |
| カネボウ | 12 | 70,860 |
【キャンペーン回数】では1位が「ロレアル(メイベリン)」で44回、2位が「Lanegine」で39回、3位の「ディオール」が31回となっています。上位3者で比べても、ロレアル(メイベリン)の回数の多さは群を抜いています。
続いて【SNS露出件数】です。年間で最も多かったのは1位「ディオール」592,080件でした。2位は「ロレアル(メイベリン)」で551,056件、3位は「資生堂」の386,848件となっています。
二つの指標から、ディオールは中国への投資に積極的な姿勢があり、かつSNSへの露出では成果が出ているということがわかります。ロレアル(メイベリン)も同様、キャンペーン実施にはかなり積極的な姿勢があり、その成果は確実に数字に表れています。
日本ブランド、微博のトップページに現れる違いは色以上
一方でSNS露出件数3位の資生堂は、キャンペーン回数は多くありません。キャンペーンがSNSの露出に影響を与えていない、あるいはキャンペーンごとにSNSの露出件数に与える影響の大きさが異なるといった状況が考えられます。
キャンペーンの詳細は(3)にてご紹介予定です。本編ではまず、日本のブランドに焦点を絞って、その後欧米ブランドと合わせて、SNS露出件数の多寡に影響する要因を考察していきたいと思います。
調査対象のうち、日本のブランドであるコーセー、カネボウのキャンペーン回数は資生堂とそこまで大きな差が開いているわけではありません。ところが、SNS露出件数では大きな差が出ています。この点にもキャンペーンの影響力という要因が作用しているとも考えられますが、他に考えられる点はどこに存在するでしょうか。
SNSの微博の公式アカウントを確認してみます。
まずはフォロワー数です。コーセーのフォロワー数は8万、カネボウはECモールの天猫の旗艦店の微博アカウントでフォロワー数約2.5万となっています。
アカウントのデザインに着目すると、コーセーは基礎化粧品を、カネボウは「メイクアップ化粧品」を押していることがわかります。これらのアイテムの違いが現在のSNS露出件数の明暗を分けているのかもしれません。
ちなみに「資生堂公式アカウント」はフォロワー数43万、トップページはピンクを基調にリキッドファンデーションを前面に出したデザインとなっています。同時に運用している「資生堂中国」のアカウントはフォロワー数21万、赤を基調とした基礎化粧品を配置したトップページとなっています。後者は本年2月に開設されていますが、「基礎化粧品」と「メイクアップ商品」を切り分けるブランディングを狙ったもののようにも見えます。

▲KOSEの微博公式アカウントトップページ。雪肌精と「青」を前面に出している

▲カネボウの微博公式アカウントトップページ。

▲2017年2月に開設された資生堂中国の微博公式アカウントトップページ。
訪日中のクチコミでは、企業別商品件数は露出件数とリンク
訪日中のコスメ購入の場面では、各ブランドの商品件数とクチコミ件数に関連性が見られるのでしょうか。トレンドViewerの「企業別商品数ランキング」の9月6日~12日における集計結果をとりあげ、比較したいと思います。
※「買ったランキング」に入った商品数の多いブランドを集計。
同期間の「企業別商品数ランキング」1位は「資生堂」で、31商品がランクインしました。言及数は9,221件となっています。8位に今回調査した「カネボウ」(10商品、3,896件)、9位に「コーセー」(9商品、3,186件)がランクインしています。
資生堂は中国で展開している商品も消費者に認知されている商品も多岐にわたり、これが露出件数の多さにも結び付いていることが考えられます。
コーセー、カネボウはそれぞれ中国でのスター商品といえる人気アイテム(雪肌精、Freeplus)の地位は確立しているものの、資生堂と異なりそれらの商品だけに頼って知名度を確保している状態のようです。
資生堂には「アネッサ」「パーフェクトホイップ」といった定番人気商品が複数あり、またコーセーには「雪肌精」という看板商品があります。こういった定番商品がブランドへの信頼を築き上げ、ほかのラインへ手を伸ばす動機付けの一端を担うのではないでしょうか。
逆風にさらされる韓国製品
さて次に韓国のブランドに視点を移してみます。
中国で人気の韓国の化粧品といえば「イニスフリー」と「Lanegine」です。「イニスフリー」はキャンペーン回数24回/SNS露出件数171,716件、「Lanegine」はキャンペーン回数39回/SNS露出件数164,384件となっています。
両者とも、キャンペーン回数の割にはSNS露出件数が伸び悩んでいるようです。イニスフリーのキャンペーン回数はランコムの29件に迫る勢いですが、ランコムの露出件数は約37万8,000件と倍以上の差がついています。
Lanegineは今年、中国での販売がちょうど15周年を迎えており、2017年9月末からさまざまなキャンペーンが打たれています。中国での販売にも実績があり、これから認知拡大…というフェーズでもなさそうです。本来ならさらなる消費拡大も期待できそうな局面にも思えますが、この勢いはどこでそがれてしまったのでしょうか。
実は「韓国の化粧品」は2年ほど前まではかなりの人気を博しており、「若い女性のマストアイテム」と目されていました。ところが昨年末のTHAADの配備以降、化粧品に限らず韓国製品のCM、韓国のタレント、韓国ドラマの放映、出演がぐっと減っています。それに伴い消費者が韓国製品を目にする機会も減り、加えて消費者自身にも「嫌韓」のトレンドが広まっています。
「ブームになる加速力も大きいが、ファンが離れるのも早い」-中国市場の厳しさを味わうしかないのが今の韓国製品なのかもしれません。一時は中国の女子コスメ市場を席巻した韓国ブランドは寒い冬を乗り越え、季節の移り変わりとともに春を迎えることができるのでしょうか。
まとめ ~商品ラインナップの多さが肝
ディオールはじめとする欧米ブランドの微博フォロワー数は約130~200万で、微博のトップページからは商品ラインナップの多さが読み取れます。こういったSNS露出件数において「成功している」欧米の化粧品の事例と、日本の露出件数が後塵を拝している現状を合わせて考えてみれば、日本ブランドは「基礎化粧品」や特定の商品のイメージがブランドに紐づけられていることが露出件数の少なさにつながっているということも考えられます。次の人気商品、メイクアップ商品やファッション、そのほかのカテゴリでの商品展開を認知してもらうことで、キャンペーン後の露出件数の増加を見込めるのではないでしょうか。
続いてそれぞれのブランドの「キャンペーン実施回数」と「SNS露出件数」を時系列に整理して、両者の関係やブランドごとに共通した特徴を探ります。
▼続きはこちら
対決シリーズ!【欧米vs韓国vs日本】化粧品の場合(2) ~キャンペーンは最低月一回、勝者は秋だけでなくて○○にも実施していた!~