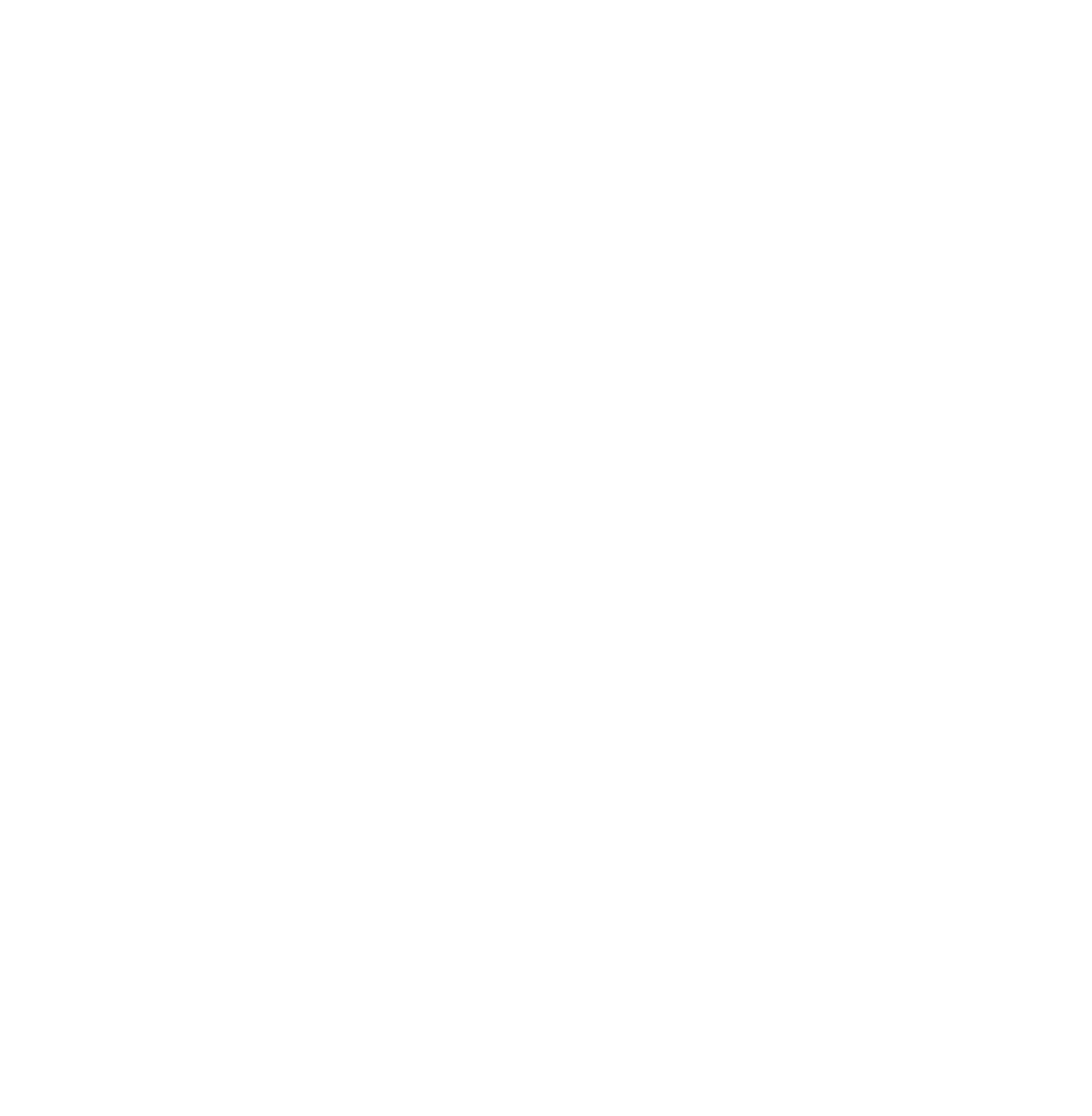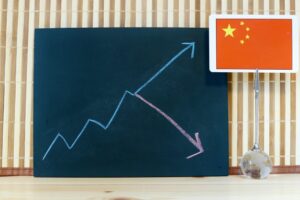草場歩-ものづくり産業部・生活関連産業課課長代理
近年の越境EC市場の盛り上がりによって、多くの日本企業が参入しています。しかし同時に越境ECに関して「興味があるけれど、慎重にならざるを得ない」という日本企業はまだ多く存在しており、そうした日本企業の声が日本貿易振興機構(JETRO)にも数多く寄せられているとのこと。今回はそのJETROにおける越境ECのスペシャリスト、ものづくり産業部・生活関連産業課の草場歩課長代理にお話を伺いました。
目次
「今からスタート」も多い日本企業の動向
ー徐々に活発化している日本企業の越境ECへの進出ですが、草場さんの感じる大きな状況の変化としてはどういったものがありますか?
草場歩氏(以下、草場):2015年から2017年にかけては、越境ECに関する問い合わせがJETROに対して 年間1,000件以上あり、日本の企業にとっても比較的関心の高い分野であると認識しています。特に、2016年は中国で越境ECに関する制度変更がありましたのでそれに関する問い合わせが急増した時期がありました。
最近は一定の落ち着きをみせてきたという感じですが、「越境ECでモノを売りたいけれど、何をすればよいのか?」といった越境ECへの入り口に関するものから、「(中国側から)こういった書類を提出しろと言われたが、本当に必要なのか?」といった具体的業務の疑問など、実に様々な内容の問い合わせが来ています。
ーすでに進出している日本企業も増えていながら、「まだまだこれからスタート」という企業も多い、ということですか。
草場:そうですね、企業によって取り組みの状況はバラバラ、といった印象です。JETROでは中小企業の海外展開への支援などをやらせていただくことが多いのですが、今まで国内市場のみに目を向けていた方々も、最近になって「海外にも目を向けたい」と考え始めています。そうした企業にとって、海外進出の中でも越境ECは比較的取り組みやすいといった認識があるのではと思います。
また、ここ2~3年で顕著なのは、中国の大手ECサイトの方が日本で拠点を設立し、日本での商品開発、もしくは商品の買付に乗り出していることですね。代表的な企業名を上げれば、京東(JD)や唯品会(VIP)やネットイース・コアラ(KAOLA)といった企業です。
これらの企業は地方へ行ってセミナーを行なったり、企業の発掘を行なっているようです。日本での知名度も上がっていて、セミナーを行なうと定員がいっぱいになるような状況。日本企業の関心も引き続き高いようです。
ー実際に越境ECに取り組みたい、となった時に、前段階として、その企業の中国への理解や認知度といったところは、いかがでしょうか?
草場:前述のように企業の状況によって、認識にもばらつきがあるというのが正直なところです。
何年も前から中国と取引があって現地の状況をご存知の企業であれば、市場拡大についての情報もあり、その収集意識も高いように見受けられます。
しかし逆にあまり中国との接触がなく、中国へ行ったことがないという企業の方は、日本国内の報道に頼ってしまうことが多いようです。報道されている内容の中にはネガティブなものもあるために、そのマイナスなイメージを引きずり、不安になってしまっている方もいるようです。
ー海外進出に関して情報は死活問題。特にこれから進出を考える企業にとって、いかにして正確な情報を取得していくは、非常に大きな課題になっているようですね。

「中国政府は越境ECを含めた市場の正規化に取り組んでいる」と語るJETROの草場課長代理
規制は厳格化?それとも緩和? 気になる行方
ー情報収集とはいうものの、変化が激しい中国市場。現在JETROから見て、現在の越境ECで日本企業がつけるべきポイントとは?
草場:何よりも、中国の法律に順応していくことだと思います。
ご存知の方も多いのですが、昨年3月15日の消費者権益の日に「日本の食品のなかで本来輸入が禁止されている一部の商品が、越境ECで大量に流入している」といった問題が報道され、中国のECや市場から日本製の食品が一度になくなったことがありました。
これに見られるように、中国政府は「(越境ECを含めた)市場の正規化」に取り組んでおり、今後もこういった急な事態が生じる可能性があります。それに毎回対応できる柔軟性は必要ですし、必要なプロセスを踏んだ正規の取引である商品をどう拡大していくか、が重要だと思われます。
また、越境ECのなかでも保税区モデルについては、中国市場で化粧品や食品の販売をする際、CFDA(国家食品薬品監督管理総局)の輸入販売許可を商品ごとに取得することが義務付けられるという政策が打ち出されています。
現在はその施行が2018年末まで引き延ばされている状況ですが、施行されるかどうかも現時点では未定の状況。今度の動向については注意深く注視していく必要があります。
ーこうした中国政府による市場整理の取り組み、印象としては「厳格化」を押し出しているように見られ、日本の企業にとってはハードルが上がっているように感じられます。何か緩和の兆しなどはないのでしょうか?
草場:厳格化だけではないように思います。
例えば北京の中国日本商会(※)では毎年「中国経済と日本企業白書」と呼ばれる刊行物を取りまとめて、同時にそれを現地当局に対する意見書として提出しています。同白書においては長年、日本製食品の輸入について規制緩和を求めてきましたが、原発事故以降は目立った動きはありませんでした。しかし、今年1月の報道においては、両国政府の実務者レベルでミーティングの場を持つことが紹介され、緩和に向けて動き出すのではとの期待を感じさせます。
ーこれは非常にうれしい知らせですね。
草場:もちろん現段階では流動的なので断言はできません。しかし食品に関して言えば、中国では生鮮食品を越境ECや通販で購入している消費者も少なくなく、日本産の食品についても、現地でのニーズは高まっているので、規制緩和がもたらす好影響を期待しています。
また、前述の保税区モデルの越境EC、化粧品におけるCFDA(国家食品薬品監督管理総局)の輸入販売許可に関しても、現在上海で試行されている「届け出制」では、その手続き期間も従来の半年以上から3~4か月程度と大幅に短縮されています。将来的にはこの届け出制が全国に広がる可能性があります。
さらに、中国ではIT技術の発展に伴って各事業所、あるいは個人への「信用評価制度」が様々な形で導入されています。これらを活用して市場の健全化を図っていく流れにはなるのではないかと思います。
関税が上がる?下がる? 消費者心理は…。
ー日本の企業にとっては、中国における関税などの税制面も変化が激しく、把握に苦労しているようです。
草場:これまで越境ECでの輸入については関税がかかっておらず、これが従来型の貿易とは違った越境ECの強みとなっていました。しかし、正規の貿易についても徐々に関税は引き下げられており、2017年12月にも消費材の関税が一段階引き下げられ、2015年以降4回目の引き下げ改定となりました。
このように、徐々に従来型の流通に掛かる一般貿易の関税を下げることで、国内の従来型小売店舗販売商品と越境ECとの価格差を縮めていく方針だと考えられます。
ー従来型の正規輸入での店舗販売が、価格面でも越境ECと同等に戦えるようになっていく、ということでしょうか?
草場:そうですね、中国としても、政策として越境ECを推進している反面、従来型の小売業者からの反発を抑えるためにどうバランスをとっていくのか、が課題の一つになっていると思います。そこで一般貿易についても税制面の優遇がなされていると考えられます。
ちなみに中国では商品の値段が内税表記です。消費者も商品の購入時には、関税などの税金分もすべて織り込まれた価格表記を見て比較していることになります。
ということは、関税が下がることで店頭で見かける輸入商品の価格も下がり、消費者にとっては同様の価格帯で購入できる選択肢が増える、といった形になります。
ー中国政府も、いまは越境ECというビジネスモデルがようやく出来上がってきたところで、この部分に関してどういった規制をかけるのか試行錯誤といった形でしょうか。
草場:そうですね、段階的に様々な形のチェック体制を整えていくよう、現状ではいろいろと試しているところだと思われます。
いずれにしても、日本企業が出来ることとしては、どういった手続きが必要になったにせよ、それに対応できるよう準備をしておくことが重要だと思います。
以前は越境ECに価格的な優位性があったものと従来型の貿易を経た商品との、価格面での差が縮んでいくとなれば、メーカーや小売りにとって、競争は激しくなってきます。
次回はそうした競争が激化する中で、中国人消費者に選ばれるためにはどうすれば良いのか? また、今後の見通しについて、お話を伺っていきます。
1991年4月22日に中国政府から中国における外国商工会議所の第一号として正式に認可された日系企業の団体。中国に設立・出資した日系企業間の交流、日中経済交流の促進を図るほか、2011年4月からは、在中国の日系企業を代表する団体として、ビジネス上の隘路改善を求める意見・要望や、中国経済発展に資するための建議を盛り込んだ「中国経済と日本企業白書」を毎年発刊している。