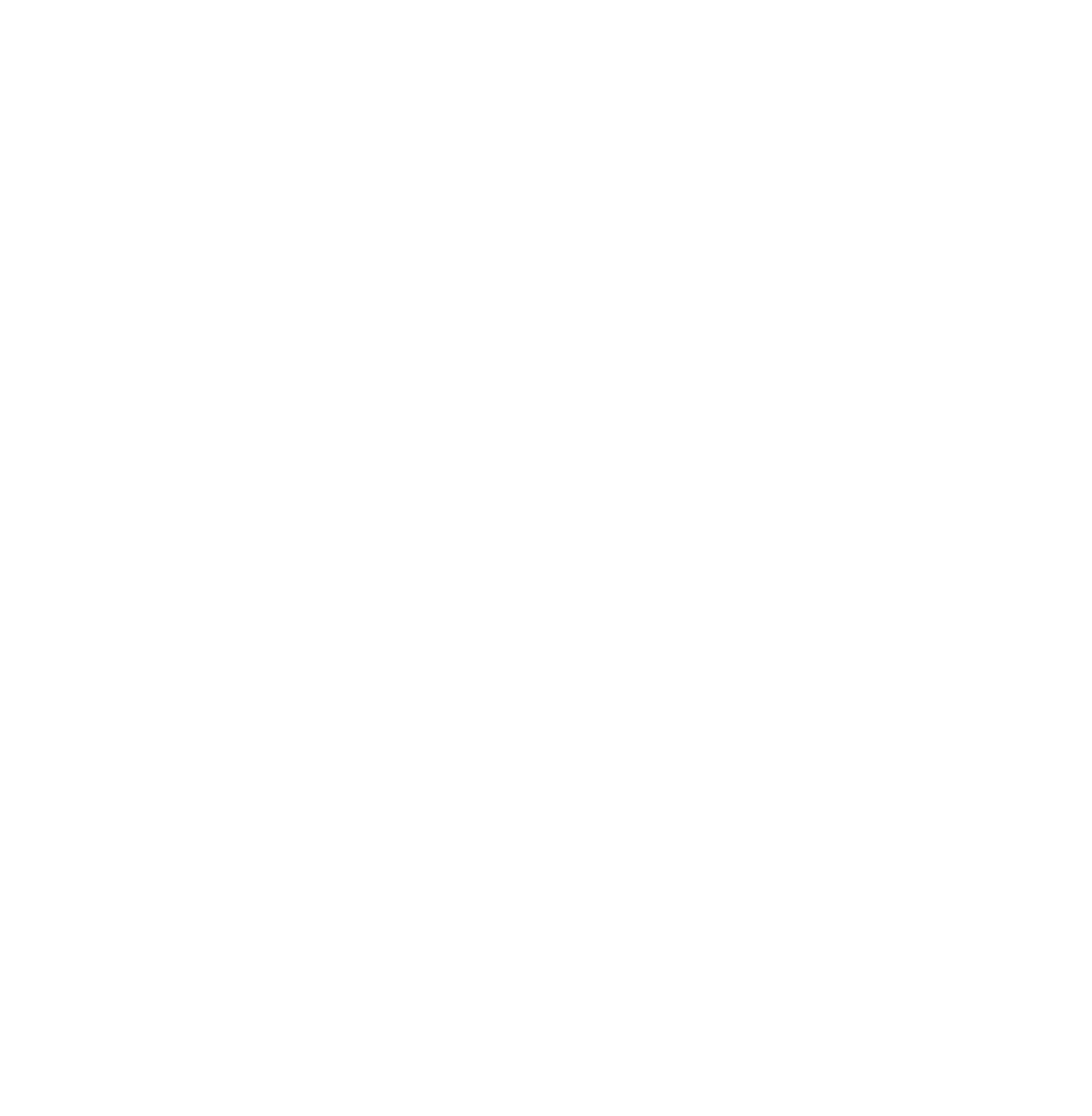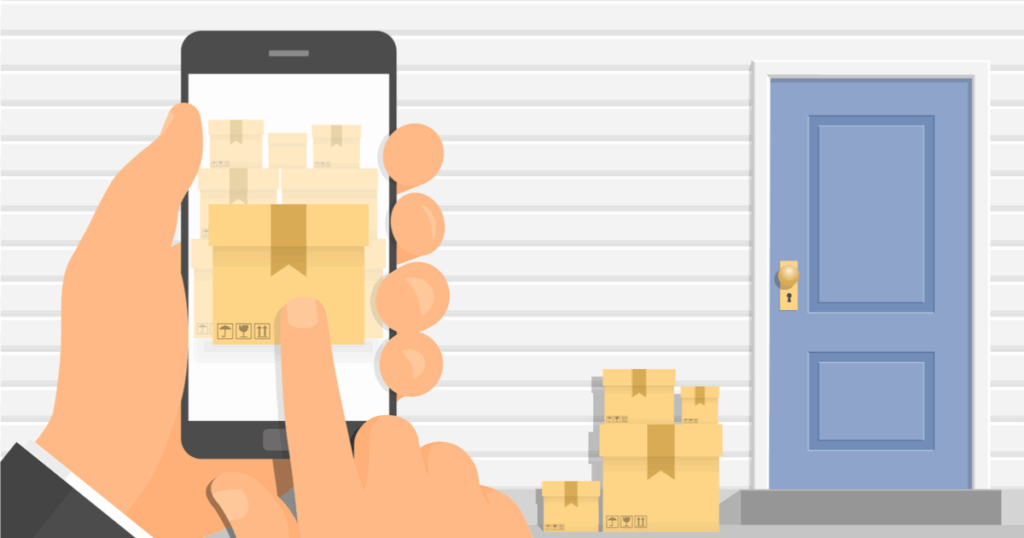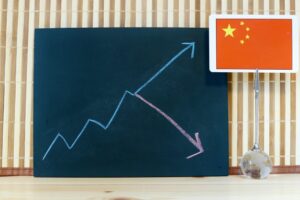巨大な消費大国となった中国。多くのメーカー、小売り業が進出していますが、彼らを阻むのは中国消費者の変化。すでにその中心は伝統的な小売業から新たな販売チャネル「EC」へと移っています。その中国市場で、日本の小売業としていち早く越境EC事業を展開したのが三越伊勢丹。同社の天猫旗艦店においてはすでに多くのファンを獲得し、実績を上げています。しかし、それは決して容易な道でありませんでした。今回は同社に日本の小売業としての中国EC事業の道のり、そしてその中で行ったSNSビッグデータを基にしたWEBメディアプロモーション、KOL施策などについてお話を聞きました。第一回は中国プロモーションを展開するその背景について語っていただいています。
株式会社三越伊勢丹
百貨店事業本部EC事業部
EC推進(越境MD)バイヤー
合田郷史
海外事業本部
海外営業統括部MD担当
バイヤー
吉田正輝
インタビュアー:濱野智成 株式会社トレンドExpress代表取締役社長
■行った施策
- W11向けのトレンドPR×KOL施策。
- 事前分析によるプロモーションインサイトの発掘と15メディア×3回の配信。
- KOLもビッグデータ分析に基づき選定し、コンテンツを開発。新浪微博にて計4名によるコンテンツを配信。
■結果
- 訪問客数は施策前と比較して300%以上に成長し、大幅な売上アップ
- 天猫旗艦店のファン数も400%以上増加し、顧客資産を形成して継続的な売上アップ
目次
中国市場の動きと三越伊勢丹-中国小売市場の変化
ー三越伊勢丹さんと言えば中国国内でも店舗を構え、中国の消費者からの評価も非常に高いイメージがあります。その御社が天猫に旗艦店を出店された背景についてお聞かせいただけますか?
合田郷史(以下:合田):まず弊社は上海をはじめとして天津、成都にも店舗を構え、同時に小型ショップも展開しています。中国における商売はすでに20年以上にわたりますが、お話にあるように2016年11月、中国越境ECサイトの大手である「T-Mall Global」へ出店をいたしました。
その背景は、ご存知のことと思いますが、百貨店を含めた小売業は現在、実店舗での売り上げはどこも伸び悩んでいるという現状です。
その原因は消費者の消費の場が従来の小売(百貨店やモール)からECにシフトしていることにあります。そのため我々は、ECそのものの将来性にも注目、国内でも戦略的にECを活用する必要があると考えてきました。
なかでも、市場規模においても日本よりもはるかに大きく、非常に魅力的な市場である「中国向けの越境EC」市場に進出したのです。
実はこの中国越境EC市場に日系の百貨店はこれまで進出していません。私たちはこれまで培ったノウハウに加え、先行進出というメリットを享受できるという強みも鑑み進出に踏み切りました。
吉田正輝(以下:吉田):そうですね、少し補足させていただくと、中国市場というのは「粗削りだが非常にポテンシャルのあるマーケット」。国土の広さ、人口の多さを考えればお分けりいただけると思います。
その市場に対し、私たちは確かに25年の歴史を持っていますが、では「中国全土で知名度があるか」と言えば、決してそうではありません。
こうしたリアル店舗ではフォローしきれない地域への知名度を、オンラインで補い、広めていくことも、越境ECのメリットだと考えています。
ーなるほど。ただ、中国、特に上海では多くの百貨店やモールが立ち並び、華やかな印象です。さらには地方都市にも広がっており、まだチャンスはあるように思いますが?
合田:確かにハイエンドモールや大型SCは地方にも数多くできています。ですが、物販に関しては売れているとは言えない現状にあり、市場からみれば百貨店は厳しい状況にあると感じられます。わたくしも上海に赴任した経験がありますが、そういった印象を受けました。
問題は「オフラインにおける物販の実情は、新しいコンテンツに枯渇している」ということだと思います。新しい百貨店やモールを見てもインターナショナルブランドは入店しているものの、それは日本ほど充実していないように見えます。
それに比してECは比較的適正価格で国際ブランドを購入することができます。それこそ、ECが急成長している理由だと思います。

「中国の百貨店ビジネスも難しい環境にある」と話す合田氏
三越伊勢丹・日本のメーカー・世界の消費者をつなげる存在へ
ーとは言いながら、小売店として越境ECは成功事例も少ない市場です。決定に至るには社内的なハードルと言いますか、相当な葛藤があったのでは、と拝察しますが。
合田:そうですね。しかしこの数年、国内小売業は中国人顧客の売り上げシェアが大きな比重を占めています。三越伊勢丹をみても、百貨店としては国内での免税販売が多い店舗。2016年にも、3年前に比べてインバウンド売り上げが4倍にもなっており、さらにその7割が中国のお客様。その消費は無視できないレベルとなっています。
国内消費は縮小しているなか、この日本商品や店舗の魅力を中国消費者に伝える必要、それを通じて新しい顧客づくりが課題となっています。これは日本の小売りにとっても避けられないのではないでしょうか。
ーそれが中国の越境ECだったわけですね。
合田:そうです。この越境EC市場にはすでにドラッグストア、化粧品メーカーが積極的に進出しています。
ただ、大手メーカーなどは自前で旗艦店を出店する体力を有していますが、中小のメーカーでは商品力と人気があっても、大手のプラットホームへ進出するためのハードルが高いです。
そこで、我々三越伊勢丹が中国の越境ECに進出することで、日本のメーカーが出品できるチャンスを創出する。そうすることで、メーカーだけではなく、中国の消費者にも喜んでもらえる商品が展開できるように思います。
これはすなわち、百貨店が百貨店としての責務を果たすということになります。
さらに前述のように日系百貨店はこれまで進出していません。この市場に先駆けて進出し、インバウンドのお客様が日本の店舗で購入し、そしてそれを中国に帰国した後、越境ECで再び購入するというサイクルを作り上げることができると思っています。
そのサイクルの中で、「三越伊勢丹っていいよね」というイメージが定着し、中国の伊勢丹店舗で買い物したり、また日本に来た時に日本で買い物をしていただく。そしてその間にも家族、友人に、口コミで拡散し、また伊勢丹のイメージが高まっていく…。こうしたサイクルをしっかり行って日中のブランディング向上と顧客の囲い込みを図る、そうした視点からこの事業はやるべき事業であると考えているところです。
ーお話を伺っていると、グローバルのオムニチャネル、「global to global」ともいえる視点からビジネス展開をされているように感じますし、さらに言えば規模は大きくないがよい商品を持った企業の販路拡大という点も、三越伊勢丹の理念が事業化しての越境ECビジネスになっているようにも思えます。ただ、社内で反対の声というのはなかったのでしょうか?
合田:反対というよりは、「簡単に儲かるような事業ではない、出足はそうとう苦労するだろう」という見込みはされていました。しかし、そのマーケットの大きさ、成長性を鑑みれば、我々だけではなく出品していただいているメーカーさんも、2~3年後には結果を出せるところまでは持っていけると判断し、社内にも説得をしました。
また中国のマーケットもスピードが命ですから、これに追いつくために、2016年上半期には経営会議などで早急に判断してのことです。
ー日系は失敗を許容できないという特徴はあるようですが、三越伊勢丹さんは失敗を恐れず、果敢にチャレンジしているようにも見えます。
合田:そこまでではないと思いますが、変化を恐れないこと、例えダメでもトライする価値があることに対しては理解があったと思います。
吉田:越境EC自体は「顧客と三越伊勢丹の接点」、「企業と三越伊勢丹の接点」。今はまだ「小売りが越境EC参入は厳しいのでは?」という声もあります。
それは自分たちでも理解していますが、それでいてなぜこの事業をやるのかというと、一つには先ほど申し上げた自分たちの「役割」によるところも大きいこと、そして非常に大きな伸びしろがある中国のEC市場で、利益が出る構造を作り上げなくてはならないという「使命感」によるところが大きいと思います。
事業として成立していくために早い段階で利益生み出していかなければいけません。そこは、我々も常に努力しているところです。
ー日本のインバウンドで伸び、そして客接点を最大化していく。日本の市場縮小のなかで苦労していくであろう企業、アンテナを張っている企業さんのために販路を拡大していく。そのために伸びしろのある大きな市場でチャレンジを行っているわけですね。ありがとうございました。
さて、次回はいよいよ本番。中国マーケティングについてお話を伺っていきます。
▼次回はこちら