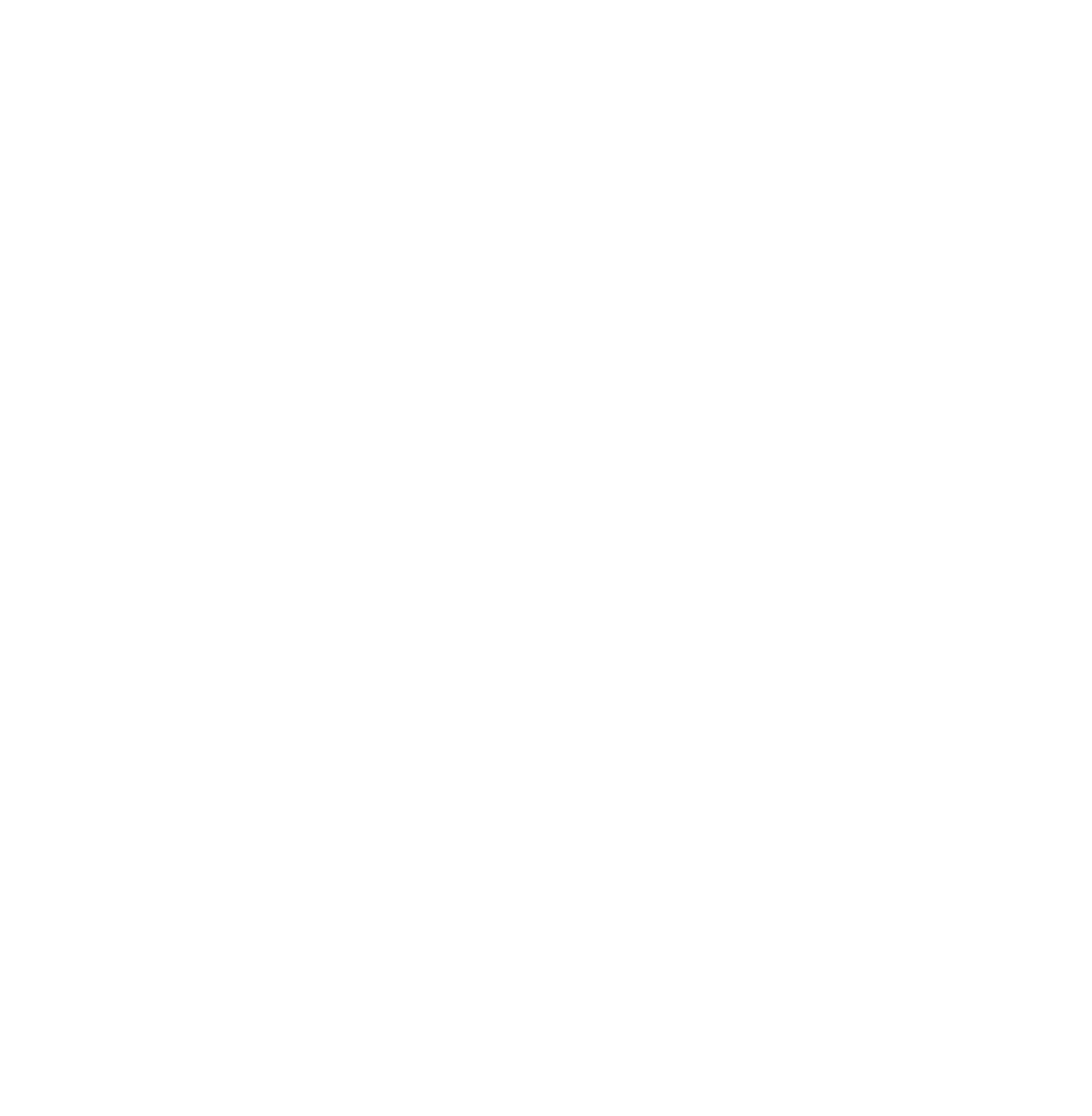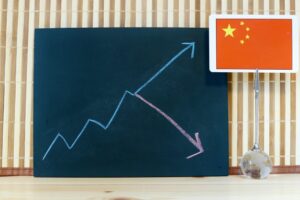日本の小売業としていち早く中国のEC市場に進出した三越伊勢丹。いまでこそ同社の天猫国際(T-Mall Global)旗艦店においては多くのファンを獲得し、実績を上げていますが、そこには並みならぬ苦労があった模様。今回はそんな同社の展開初期の状況や、打開策となったSNSビッグデータ、そしてそのデータを基にしたWEBメディアプロモーション(KOL施策含む)などについてお話を聞いていきます。
株式会社三越伊勢丹
百貨店事業本部EC事業部
EC推進(越境MD)バイヤー
合田郷史
海外事業本部
海外営業統括部MD担当
バイヤー
吉田正輝
インタビュアー:濱野智成 株式会社トレンドExpress代表取締役社長
■行った施策
- W11向けのトレンドPR×KOL施策。
- 事前分析によるプロモーションインサイトの発掘と15メディア×3回の配信。
- KOLもビッグデータ分析に基づき選定し、コンテンツを開発。新浪微博にて計4名によるコンテンツを配信。
■結果
- 訪問客数は施策前と比較して300%以上に成長し、大幅な売上アップ
- 天猫旗艦店のファン数も400%以上増加し、顧客資産を形成して継続的な売上アップ
▼前回の記事はこちらから
【中国プロモレポート】 日本小売の挑戦 ビッグデータでW11を切り開く(1) ―株式会社三越伊勢丹
目次
初の越境モデル、苦戦でのスタート
ーさてここからは本格的に中国国内でのマーケティングについてお話を伺っていきたいと思います。まずはT-Mall Global旗艦店オープン時期の状況についてお聞かせいただけますか?
合田:お店は2016年11月にソフトオープンしました。まさにW11直前にオープンしましたので、品揃え、業務オペレーションなども間に合わず、その年はキャンペーンへの参加を見送りました。
その半月後の「ブラックフライデー」でも、プライベートブランド中心の品ぞろえ。リリースなどを行いましたが、なかなか認知されない。
店舗の存在もそうですが、扱っている商品も中国であまり知られていないブランドが多く、少ない売り上げに非常に苦労した日々でした。
そのため、最初の半年は品ぞろえのバリエーションを増やすこと、そして店舗の存在を中国消費者に知ってもらうことに注力しながらも、中々実績が上がらない厳しい時期でした。
ーそれは非常に大変な状況でしたね。日本の小売りトップクラスの三越伊勢丹でもそこまでの苦戦だったんですね。
合田:はい。ただ17年3月にそれまでの交渉の成果が実り、中国未進出の日系化粧品ブランドの参入が決まりました。そして3月8日の婦人節のタイミングで「THREE」(化粧品)を越境による本格展開を行うことになりました。
この時、同時に上海伊勢丹でプロモイベントを展開しています。
オフラインで実際に商品サンプルを手に取っていただいたり、メイクショーなどのイベントを行い、ブランドや商品を細かく紹介し、それをオンラインへ導くという施策を行いました。
この施策時に、KOLを使って「直播(ライブ配信)」を行いましたが、そこがターニングポイントとなり、認知度も売り上げも伸び始めたのです。
そこから5,6月(半期バーゲン)に、続けて「RMK」「松山油脂」「イースタンダード」などの人気ブランドをラインナップ・展開できるようになりました。
インバウンドでも人気の高い力のあるブランドも新たに増えたことで、ようやく売り上げ、客数の向上が目に見えてくるようになっていきました。
そういった状況で、2017年のW11を迎えたわけです。

「厳しい状況が続いたが、3月8日の婦人節でのプロモーションがターニングポイントになった」と当時を振り返る合田氏
ー2017年のW11、売れる商品が見えてきた、まさに「いける」という状況で向き合うことができたわけですか。
合田:売れる商品が見え、それをW11に向けてしっかり投入していけば十分に戦えるのではと思いました。
またW11前の9,10月にさらに新ブランドを導入し、品揃えのバリエーションが広がったことで、お客様の選択肢を増やすことができました。
ただ、ローンチ以来様々なPR施策を打ってきましたが、費用対効果が十分とは言えませんでした。実際に成功したこともありましたが、大きな失敗もありましたね。自前ではできない部分もあるので、苦労していました。
そうして迎えるW11では売り上げを上げる、成果を上げるということが最大の責務でした。同時に、当時のトップセールは「THREE」で、売れる商品も決まっており、まさに不動の売れ筋商品でしたが、次のトップセラーを掘り起こしたいという思いがあったのです。
ビッグデータで見えた「何を」、「どう伝えるべきか」
ーそのなかで御社が活用したのは、ソーシャルビッグデータをベースにしたWEBプロモーションでした。その施策にたどり着いた理由はどういったものだったのでしょう?
吉田: こうした課題については、たくさんのPR会社さんともお話しさせていただきましたが、いまだに疑問になっている点がありました。
それは、「売れる」時はどう売れるのか、ということ。いったい誰が、どの情報をどうキャッチして、拡散して、波及していって売れるか、いまだにわからないのです(苦笑)。
そうした疑問を抱えながら、2017年のW11ではソーシャルビッグデータ分析を活用し、精度の高いキーワードを記事にして、KOLが情報を取得するとみられるメディアにアプローチしていくという手法を取りました。
情報の大元にたどり着いての施策だったのです。
その結果、今でも日々、数百人ずつファンが増えているのです。それはおそらく、配信した情報を中国の消費者の方がキャッチして拡散し、私たちの店舗に訪れているという形で基礎的なファンを作れたからではないでしょうか。そしてそれが一番の成果だったと感じています。

「ソーシャルビッグデータ分析で、売れる商品の情報拡散のプロセスが見えたことが大きい」と話す吉田氏
ー「三越伊勢丹」と検索すると、その2017年W11の記事が上位にやって来る。それを見た、いわば回遊しているユーザーが店舗にやってくる。これは確かに情報がストック化された結果ですね。それが今でも続いているのは、まさにエビデンスの結果かと思います。実際、W11を終えられた後、どのような感想をもたれましたか?
合田:「なぜ売れているのか」、「どうすれば売れるか」の研究があり、そのうえでメディア配信、KOLへの拡散によって、これまで得られなかった情報が得られました。
「KOL」「動画配信」では「何万人というフォロワー」に伝えることがメインになりがちですが、「どう伝えるか」「どこで伝えるか」「どういった切り口で伝えるか」を調査・分析していくべきことを実感しました。
また、分析からターゲット選定、取り上げたい商品について何度も打ち合わせし、明確に設定をし、WEBメディアを通じて配信していきましたが、結果としてW11直近からぐっと客数も伸びました。そうした成果から、こういった情報発信が非常に大きく役立ったと感じています。
2017年のW11ではKPIも達成でき、過去最高の成果でした。これがベースアップとなり、その後も売り上げ・客数ともに伸びています。数字的にも社外に誇れる数字までもう一息。期待の持てる結果だったと思います。
ーこうしてソーシャルビッグデータ分析で得られなかった情報が入ったとのことですが、その中から「なるほど」と思えた情報は?
吉田:「三越伊勢丹」と検索した結果、「T-Mall Global」が出てこなかったことですね。日本の店舗情報は多かったのですが…。越境ECの情報は知られておらず、なかなか上がってきませんでした。その結果、「日本の三越伊勢丹」というキーワードをフックに売っていくべき、という道筋が立てられました。
またブランド分析のなかでは、松山油脂の人気商品である「ゆずクリーム」がやはりヒットしていたことですね。夏も終わる時期にゆずクリームで行くかどうかには迷いましたが、やはり同商品は認知度が高いということもわかり、それもよい成果に結びつきました。
さらに、同じ小売業態としてT-Mall Globalで最も人気の高い「メイシーズ」と比較・分析して、それをベンチマークしていくことも効果的でした。
ー見えなかったものが見えてきた、といった感じだったのでしょうか。大変参考になりました。次回はこの成果と中国三越伊勢丹の今後について伺います。
▼次回はこちらから