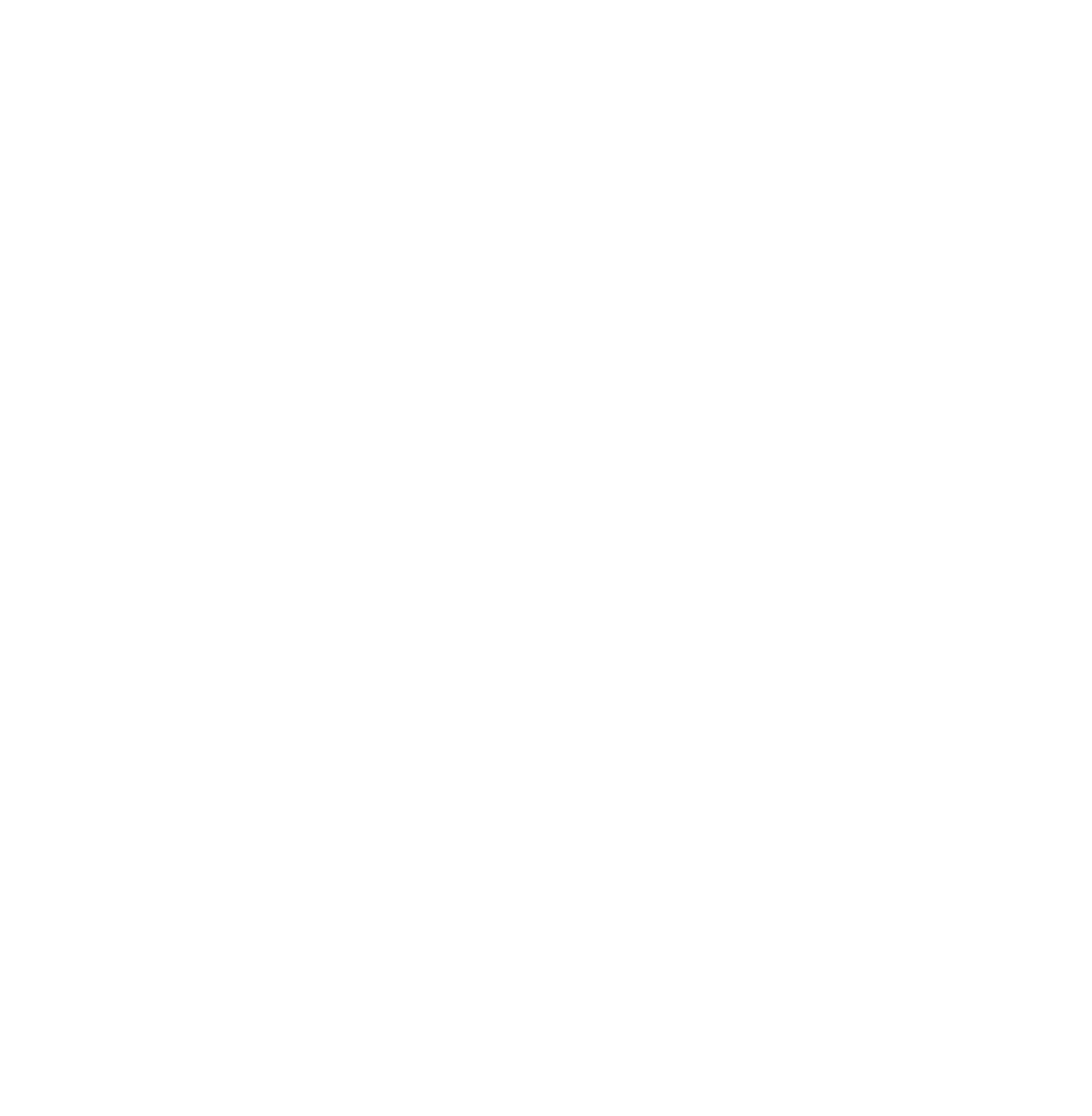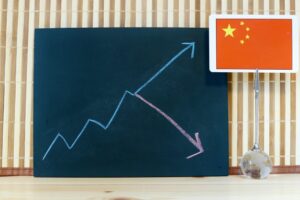2025年7月18日に観光庁から発表された「インバウンド消費動向調査」では、2025年第2四半期のインバウンド消費総額は2兆5,250億円。2024年同期比で18%の伸びを見せた。
世はコロナ後における空前のインバウンドブームである。
観光地のみならず飲食、宿泊、小売、多くの領域がインバウンドの恩恵を受けている。もちろんオーバーツーリズムなどの諸問題も存在しているものの、日本にとって大きな経済効果をもたらしていることは間違いない。
しかし実は今、日本企業が念頭に置かなければいけないのは「インバウンド」でも越境ECを中心とした「アウトバウンド」でもなく「オールバウンド」戦略の構築なのである。
インバウンドが盛り上がりを見せる今、日本企業の生命線とも言える「オールバウンド」戦略とインバウンドの在り方について考えてみたい。
目次
いわゆる「オールバウンド」とは何を指すか
「オールバウンド」という言葉を聞いてピンとくる企業やビジネスマンは今、決して多くはない。
「インバウンド」は訪日観光客、すなわち日本にやってきた観光客を取り込むための戦略である。
それに対してオールバウンドは、対象の訪日観光客が本国にいる段階である「旅マエ」から、訪日中の「旅ナカ」、そして帰国して後の「旅アト」までを一括して考える思考である。
ただその中で「刈り取り=旅ナカ」だけと考えると、それはインバウンドと何も変わらない。
そうではなく、そのどの部分でも「訴求」、「刈り取り」をフレキシブルに組み立てる構想、それをオールバウンドと呼んでいる。
代表的な例で言えば「訪日中にテスト的に使用した商品。その良さが忘れられず、帰国後に越境ECなどを用いて購入する」という消費者行動を造り上げることなどがある。
なぜ今、オールバウンドなのか
ではなぜ今「オールバウンド」という考え方が必要なのだろうか。
最も大きな要因は3年間日本からインバウンドを奪った「新型コロナ」という未曽有の事態だ。新型コロナ禍には実は大きな消費環境の変化が起こっていた。
この期間、インバウンドを失った日本の多くのブランドはオンラインによる「越境EC」にシフトした。
同時に海外を訪れられない中国などの消費者は、日本国内に住まう同国人を通じて日本の商品を購入する、ソーシャルネットワークを使って購入するシステムが出来上がった。
コロナという災害によって海外消費者が日本に行かなくても日本の商品を購入できるという環境が整ったのである。
また日系企業も中国国内での事業展開を行い、日本とは変わらぬ商品が手に入るようになっている。
しかし現在、特に最大の消費金額を誇る中国などでは消費嗜好がより細分されていくなどの変化が生じ、そこに日系以外のブランド、特に現地ローカルブランドが伸長してきている。
さらに618やダブルイレブンなどの商戦期は低価格戦略と大量のGWPが飛び交い、「日本よりも安い」という状況が生まれてしまっている。
グローバルに展開している商品ほど訪日しても「買う」という意味付けが薄らいでしまっているのである。
生活水準の向上と共に生活などの悩みが個性化され、ニーズが細分化されている中国でより顕著な現象であるが、おそらく東南アジアなども経済発展が続き中間層以上が増えてくれば、同様のことが起こるだろう。
「インバウンドと越境ECは本社、相手国内事業は現地法人」という日本企業では、自社内で競合関係が生じてしまうのみならず、双方共倒れの結果を招きかねない。
また、インバウンドのみにターゲットを合わせすぎてしまうと、訪日した際に見かけはしても手に取って体験するところまで行かない。印象を得ずに帰国してしまうと継続的なコミュニケーションも取りづらいだろう。
こうした事態を避けるために必要なのが、国境を越えた自社のビジネス環境を構築するオールバウンドの環境なのである。
オールバウンドにおけるインバウンドの在り方とは

もう少しオールバウンドの体制を具体的に見てみよう。
と言っても企業によっては規模、展開状況などが異なるためあくまでも一例として考えてほしい。
まず中核をなすのはやはり「インバウンド」である。
ただコロナ前までのように「とにかくインバウンド刈り取りを」という考えは改めねばならないだろう。
前述のように最大の消費国である中国では社会が成熟し、多くのものが国内に溢れている。簡単に言えば目が肥えているのだ。
ここでは「インバウンドのショーウィンドウ的な使い方」を述べてみよう。
まずは旅マエ。
少なくとも旅マエに「こうした人気商品が日本にある」ということを知らしめ、「日本に行ったらまずは見てみようか」という興味を掘り起こす。
特に中国に進出してない、かつ現地の日本人が日常的に使っているような商品やレギュラー商品でも日本でしか手に入らない「限定版」は「価値が高い」という印象が生まれていくのである。
そして「旅ナカ」。
ターゲット消費者が降り立った空港などでの広告でより印象付ける。
同時に人気の日本国内の商業スペースにおいてポップアップなどの体験型イベント(直接商品を手に取る)、もしくはホテルやツアーバスなどでサンプルなどを配布すると言った手段も考えうる。
日本に来ているということは、それだけ直接商品を手に取る機会に近いということでもあるため、なるべくそのチャンスを創造することである。
それで購入にまで至ればもちろんだが、好印象を持ってもそのまま帰国してしまう事も多い。
そのため重要なのは「旅アト」の仕組みづくりである。
越境ECやもしくは日本在住のKOCなどを通じた販売チャネルを活用し、購入した顧客にはリピートを、好印象をもった消費者には購入を促す流れを作っておく。
少なくとも旅ナカ中に体験した消費者がSNS上で発信していくことで、それが誰かの「旅マエ」情報になっていくという可能性も生まれる。
こうした跡切れのないサイクルを作っていくことが今後、インバウンドをきっかけとした海外ビジネスにおいては重要度を増してくるだろう。
ただ繰り返しになるが「日本本社と現地法人がそれぞれに別のKPIを追う」という従来のモデルではこうした仕組みは作りずらい。
むしろ「どのようにしたら双方が収益を上げられるモデルになるのか」を考え、トライ・アンド・エラーでも実行していくことが重要に思える。
むろん一朝一夕に進む話ではないが、今から始めておくに越したことはない。
インバウンド新局面、変わりゆく市場でピンチに見舞われる企業も多い。
それをチャンスに変える力が日本の企業には備わっているはずである。
その奮起を期待したい。
今年の3月に「インバウンドツーリズムの最新トレンド2025年の大胆予測とオールバウンド戦略事例を徹底解説」というウェブセミナーを開催し、より詳細にオールバウンドについて解説しています。
動画視聴もできますので、以下よりご視聴ください。
ウェブセミナーの動画視聴に関してはこちら