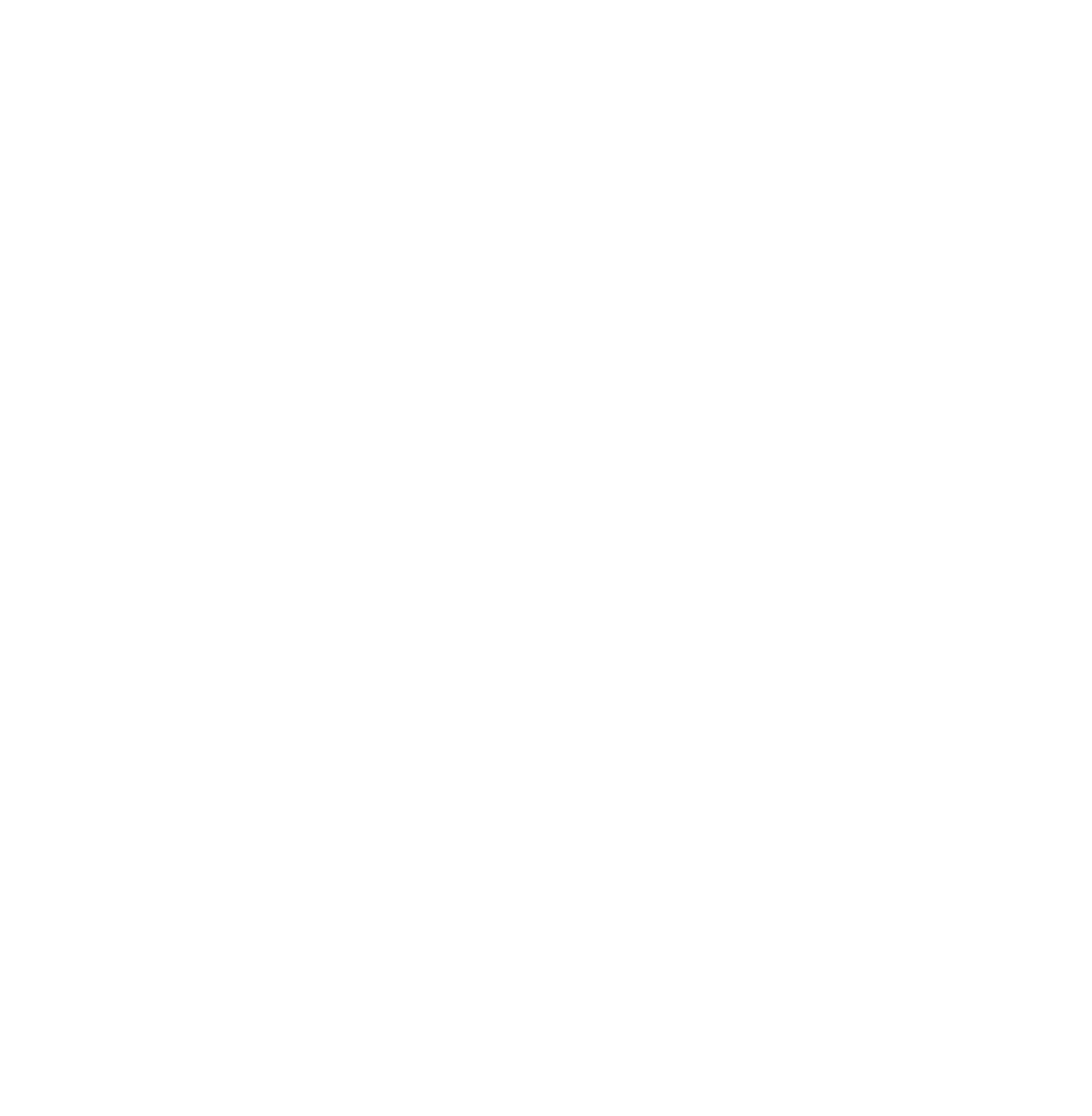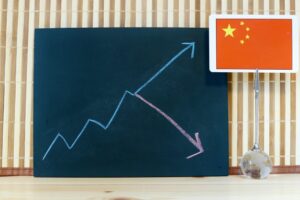2025年も半分が過ぎた。
世界情勢を見ればウクライナ戦争の継続のほかイスラエルとアラブとの紛争、さらにはトランプ関税、国内では物価高と米問題など、頭の痛い課題がオンパレードの半年であった。
その中で中国経済は各界の注目のテーマであり続けた。そしてその中国経済を支える消費動向の上半期を占う意味で関心を集めたのが上期最大の商戦「618」だ。
今回はその全体概況と結果を俯瞰し、その全体像をつかんでおこう。
目次
2025年の618商戦で何が変わったのか?
2025年の618について書こうと思ったとき、突然筆が止まった。
2024年のダブルイレブンの時もそうだったのだが、とにかく例年との変化が激しく、単純に比較ができないのである。
まずは2025年618の特徴(例年とは異なる点)を整理してみよう。
商戦期間の延長
まずは期間である。
ずいぶん早く、前倒しで始まった2025年の618は多くの人にとって「突然始まった」感があるのではないだろうか。
最大手・天猫(T-Mall)では5月13日からすでに予約期が開始されていた。
2024年から一週間近い前倒しである。
天猫だけではなく京東(JD.com)も抖音も、ほぼ同時のスタートを切った。上海在住の消費者に話を聞いたが「え?もう始まっているの?という感じだった」と笑いながら答えてくれた。
背景としてはやはり中国政府の「消費促進、内需拡大」という大方針を受けて販促機関を伸ばし、それによって消費者の消費意欲を伸ばそうという物であったと考えられる。
減額サービスの簡素化
もう一つ、消費促進のために行われたのが「減額サービスの簡素化」である。
すでに2024年にはその片鱗が見えていたが、2025年618にはさらに進行したと言える。
最大手の天猫(T-Mall)では、これまでの商戦で「総額〇〇元で〇元減額」と「店舗買い回りで〇%お得」、「このイベントに参加すると〇〇お得」などなど、多種多様なお得サービスが発行され、それらを複数合計して、最終的な買い物額が決まっていた。
結果として消費者は自身でその複雑なサービスの掛け合わせを計算せねばならず、Excelまで作って金額を記録していたという消費者もいたほどであった。
もちろんその計算方法を巡って商家と消費者のトラブルが発生するのも常であった。
しかし近年はそうしたものを取りやめ、単純に店舗側が「原価〇〇元が618で△△元に」といった分かりやすいものへと改定。
消費者がお得感を分かりやすく購入できるシステムへと移行したのである。
「種草」と「刈り取り」の再連動~小紅書×ECプラットホーム
そしてメディアが大きく取り上げたのが、中国の消費行動において大きな影響力を持つSNS「小紅書(RED NOTE)」と「ECプラットホーム各社」の連携である。
「商戦期のみ」とのことだが、「まず小紅書で商品の情報(成分、効果、感想)を理解してから」というジャーニーを有する小紅書と、実際に商品を購入する天猫・淘宝・京東などの連動は商家にとっては非常に理想的である。
以前はこうした連動ができていたが、小紅書上での広告レギュレーション強化、また小紅書独自のEC事業拡大などの背景から、小紅書とECプラットホーム間では断絶が続いていた。
ブランドとしてはいわゆる「種草」施策と「刈り取り」施策を別物として実施し、その関係値の効果測定ができずいるという手間があった。
しかし今回はその垣根を再度取り払い、「小紅書での認知・理解」から「ECでの購入」という理想的な形が一定レベルで可能になった。
ECプラットホームに出店している商家からすれば、ストレスのないマーケティング活動が実施できたのである。
続いてその結果を見て行こう。
2025年618の結果は?ECプラットホームの動き
すでに中国では商戦期にプラットホームがGMVを発表することはなくなっている。
そのため、
もっとも多く引用されている星図数据のデータを引用しよう。
国内のECプラットホームすべてを集めた「618」総GMVは8556億元と、2024年比で15.2%の増加を見せた。

トップとなったのは天猫で、次いで京東。そしてこれまでは「ライブコマース」として別に集計がされていたショート動画アプリである抖音、快手も2025年から「ECプラットホーム」として一緒に統計されている。
結果、抖音が2大ECプラットホームに食いつくという中国EC業界の状態がより如実に見て取れるようになっている。
天猫では「戦報(成果報告)」としてGMVの発表は無かったが、453のブランドが億元越えを達成し、そのブランド数は2024年比24%の増加としている。
またライブコマースの売り上げも81ブランドが1億元を超えており、昨年比で21%の増加を見せている。
また第3極を形成している抖音では6万のブランドが昨年比倍以上の売り上げを達成している点、また抖音ECにおける売上の半分以上が「店舗ライブ」によるもであったことを公表。
大手ブランドももちろんながら、果物などの中小の商家においても店舗ライブによって高い売上を上げることができている点を強調している。
特に中国の一財商学院の調べでは、各プラットホームのGMVを2024年と比べると、天猫や京東が9%程度にとどまっているのに対し、抖音は18.2%の伸び。
2024年が前年比30%以上の伸びを記録したことに比べるとややスローダウンしたように見えるが、それでも二桁成長を続けており、「GMVもおそらく京東にかなり近づいているのでは」と推測されている(https://www.jiemian.com/article/12928907.html)
日本でもTikTok Shopが開始されたが、本家の中国においてもまだライブコマースはEC業界における伸び頭でいるようである。

https://www.jiemian.com/article/12928907.html
2025年618商戦から考える今後の商戦と中国の消費
こうしたプラットホームなどは戦果を強調する2025年の618だったが、消費者の受け止め方はどうだったのだろうか?
まず小紅書の動きを見てみよう。
【グラフ】小紅書における2024年と2025年の「618」投稿の日時推移

出所:NOVARCA調べ
ECプラットホームとの連動が発表されたことによって盛り上がりを期待された小紅書上の618投稿であるが、「618」というキーワードを含めた投稿としては連動していない2024年を下回った。
商戦開始のタイミングもあり、山場には多少のずれが生じているが、商戦スタート後から最終に至るまでの投稿件数は一定を保っており、盛り上がりに欠けたようにも見える。
要因として考えられるのはマーケティング投稿は増えたものの、それによって一般消費者による投稿件数が減少した可能性。
もう一つは値下げが分かり切っている、かつそのシステムが以前よりも簡素化した2025年の618では「種草」の重要性が減少し、直接ECプラットホームへと向かった可能性である。
QuestMobileの調べでも、618期間中の小紅書のアクティブユーザー数が爆発的に増えた状況は見えない。
おそらくは日常的に情報を収取しているユーザーにとっては、「618だから小紅書を見る」というのではなく、普段から小紅書で見ている商品を直接ECで値段を確認して買う、という形がもっとも実情に近い使い方だったのではないかと思われる。

また気になるのは「36kr」などに掲載されている、618関連記事である。
終了後から複数の記事が掲載されているが
超长618“超安静”?(https://36kr.com/p/3343130094795270)
史上最乱618(https://36kr.com/p/3320713772427781)
など、2025年618に対する疑問や盛り上がりに欠けるタイトルが多い。
主な論調としては「期間が長引いたことで消費者に飽きが来てしまっている」、「単純な値下げ競争の中で、ブランド同士がけん制し合いお得感が減少している」といった点が指摘されている。
また前述の一財商学院の記事でもタイトルは「GMVは15%アップも期間は20%アップ」とのタイトルであり、短日で見れば売り上げは落ちている可能性もにおわせている。
消費者がより「理性化」し、「自分自身に必要なもの」を購入するようになった現在、大量に安く商品を購入する商戦は、その性質を変えていかなければいけないのかもしれない。
ブランドなどにとっても「2大商戦で年間の売り上げを大部分回収する」といった戦略も転換を求められる可能性に迫られている。
次回は視点をもうひと段落絞り込んで618のコスメ業界の状況を振り返り、今後の中国における商戦の在り方などを考えてみたい。